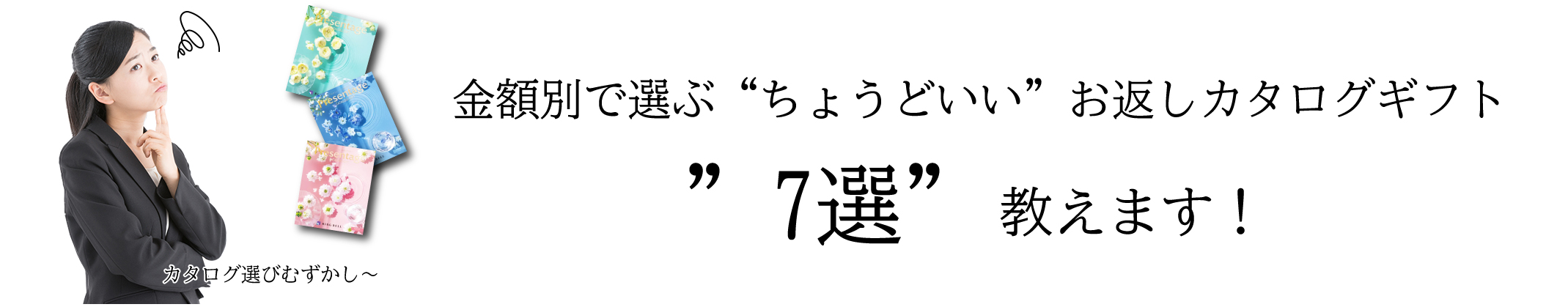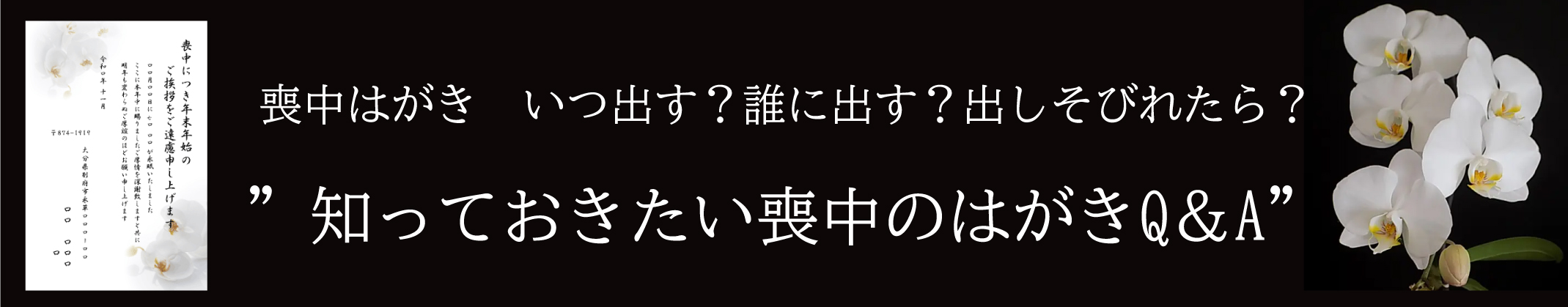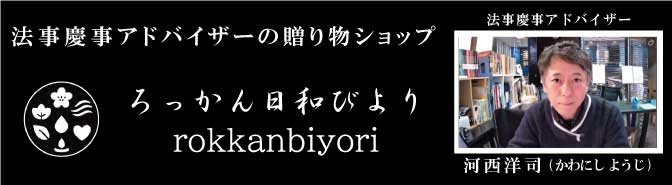家族が亡くなってから行う手続き
【時系列ガイド】
葬儀後・役所・年金・相続まで
「何を・いつ」行えばよいかを、順番にまとめました
本ページは、法事・慶事アドバイザーとして37年間、
仏事の現場に携わってきた経験をもとに構成しています。
家族が亡くなったあとには、短期間に多くの手続きが必要になります。
このページでは、死亡直後から数か月後までの流れを
時系列で整理しました。
※ すべてを一度に行う必要はありません。
「今の段階」だけを確認してください。
STEP0|亡くなった直後(当日〜翌日)
- 死亡診断書・死体検案書を受け取る
- 葬儀社へ連絡・搬送の手配
- 近親者・家族へ連絡
※ この段階では、細かな手続きよりも落ち着くことを優先してください。
STEP1|葬儀まで(〜初七日)
- 死亡届の提出(7日以内)
- 火葬許可証の受け取り
- 訃報の連絡
- 葬儀・初七日の実施
※ 多くの場合、死亡届や火葬許可証は葬儀社が代行してくれます。
STEP2|葬儀後すぐ(〜14日以内)【急ぎ】
葬儀が終わったあと、期限が短く忘れると不利益が出やすい手続きです。
- 年金受給停止(10日/14日以内)
- 健康保険資格喪失届
- 介護保険資格喪失届
- 住民票の世帯主変更
STEP3|少し落ち着いてから(〜1〜2か月)
- 葬祭費・埋葬料の請求
- 高額医療費の還付申請
- 雇用保険関係の返却
- 遺族年金・未支給年金の請求
STEP4|税金・相続の手続き(期限厳守)
- 準確定申告(4か月以内)
- 固定資産税・現所有者申告
- 相続税の申告・納税(10か月以内)
STEP5|気持ちと暮らしの整理
- 初盆・年忌法要の予定確認
- 喪中はがきの準備
- 日常を整える
故人が生命保険や共済に加入していた場合、保険金や弔慰金を受け取るための手続きが必要です。
死亡診断書(または死体検案書)・保険証券・身分証明書・戸籍謄本などが求められます。
- ● 保険会社ごとに必要書類・申請期限が異なるため、早めの確認が重要です。
- ● 団信(団体信用生命保険)付きの住宅ローンは、残債が免除になる可能性があります。
- ● 生協・農協などの共済や勤務先の互助制度も確認を。
なお、保険金の受取人が明確であれば、相続手続きとは別に受け取れる「非課税財産」として扱われることもあります。
故人が国民年金や厚生年金に加入していた場合、以下の手続きが必要になります。
特に遺族が年金を受け取るためには「遺族年金の請求」が重要です。
- ● 年金受給者だった場合: 年金事務所で「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出し、支給停止の手続きを行います。
- ● 加入中だった場合: 市区町村で「資格喪失届」などの提出が必要です。
- ● 遺族年金の請求: 子や配偶者が一定の条件を満たすと、遺族基礎年金や遺族厚生年金の対象となります。
- ● 未支給年金の請求: 亡くなった月までの未払い分がある場合、一定の遺族が請求できます。
必要書類は年金手帳・戸籍謄本・住民票・本人確認書類などです。
詳細はお近くの年金事務所または市区町村にてご確認ください。
相続が発生すると、一定の財産額を超える場合には相続税の申告が必要です。
原則として、被相続人の死亡から10か月以内に税務署へ申告・納税を行います。
- ● 基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
- ● 不動産、預貯金、有価証券、車などが課税対象となる場合があります。
- ● 税理士によるサポートや専門相談を活用するのも一案です。
なお、以下のような財産は「非課税財産」として扱われるため、相続税の対象外です。
- ● 生命保険金のうち、法定相続人1人あたり500万円までの部分
- ● 被相続人の死亡退職金(同上の非課税限度あり)
- ● 墓地・仏壇・仏具などの日常礼拝用の財産
正確な評価や計算が必要となるため、不安な場合は税務署または専門家に相談しましょう。
※本内容は、契約内容や解約条件などが変更される場合があります。最新の情報につきましては、各サービス提供元にご確認ください。
故人が受けた医療に関する費用や、加入していた健康保険制度によって支給される葬祭費などの制度があります。
また、扶養に関する社会保険関連の見直しも必要になります。
- ● 高額療養費制度: 生前に支払った医療費が一定額を超えていた場合、払い戻しが受けられる可能性があります。
- ● 葬祭費の支給: 国民健康保険や協会けんぽに加入していた場合、自治体や保険者から一定額の支給があります。
- ● 健康保険証の返却: 市区町村や勤務先を通じて返却手続きを行います。
- ● 介護保険証の返却: 要介護認定を受けていた場合は、介護保険証の返却が必要です。
それぞれ申請の期限が設けられていることが多いため、必要書類や提出先を事前に確認し、速やかに行動しましょう。
※本内容は、契約内容や解約条件などが変更される場合があります。最新の情報につきましては、各サービス提供元にご確認ください。
故人が生前に収入を得ていた場合、亡くなった年の所得について確定申告(「準確定申告」)が必要です。
また、相続に伴い相続税の申告や納税が必要になるケースもあります。
- ● 準確定申告: 故人の所得について、相続人が4カ月以内に申告・納税します。
- ● 相続税の申告: 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人)を超える場合は、10カ月以内に申告・納税が必要です。
- ● 延納・物納制度: 相続税を一括で納められない場合は、延納・物納制度の検討も可能です。
- ● 税理士への相談: 相続財産の評価や配分に不安がある場合は、専門家に相談するのが安心です。
税務関連の手続きは期限が明確に定められており、後回しにするとペナルティが発生する可能性もあります。
早めに準備・相談を進めましょう。
※本内容は、契約内容や解約条件などが変更される場合があります。最新の情報につきましては、各サービス提供元にご確認ください。
故人名義で契約していたライフラインや各種契約を、相続人名義に変更または解約する必要があります。
放置すると利用料金が発生し続けたり、トラブルの原因になることもあるため注意が必要です。
- ● 電気・ガス・水道: 使用継続するかどうかに応じて名義変更または解約を。
- ● 固定電話・携帯電話: 解約手続きには本人確認書類や死亡診断書のコピーが必要な場合があります。
- ● インターネット・プロバイダー: 契約内容に応じて違約金が発生するケースもあるため要確認。
- ● NHK・新聞・定期購読: 引き落とし口座の停止前に各社へ連絡を。
- ● 運転免許証・パスポート: 公的身分証は必ず返納手続きを行いましょう。
一部の契約では「死亡をもって契約終了」となるものもあります。
各契約先に早めに確認・連絡を入れ、トラブル防止を心がけましょう。
※本内容は、契約内容や解約条件などが変更される場合があります。最新の情報につきましては、各サービス提供元にご確認ください。
故人が日常的に利用していたサービスや、施設・団体への登録についても、不要であれば速やかな手続きが必要です。
放置すると利用料金や年会費の請求が継続する恐れがあります。
- ● クレジットカード: 各社へ連絡して解約。未使用分ポイントの取り扱いにも注意。
- ● 会員サービス: スポーツジム・動画配信・通販サイトなどの定期契約を確認し、解約手続きを行いましょう。
- ● レンタル品: 医療機器・介護用品・書籍など、レンタル契約中のものがないか確認を。
- ● 図書館・自治体施設: 図書や備品の返却、登録解除の確認も忘れずに。
- ● 各種会員証やカード類: ショッピングモール、ポイントカードなども含め整理しましょう。
故人の名義で継続している契約がないか、家族で一度一覧にして確認すると安心です。
※本※本内容は、契約内容や解約条件などが変更される場合があります。最新の情報につきましては、各サービス提供元にご確認ください。
本ページの内容につきましては、十分な配慮のもと作成しておりますが、 その正確性や完全性を保証するものではありません。 本ページの情報をもとに行われた手続き等により生じた結果については、 恐れ入りますが当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
▶ 頂いた金額で選ぶ、“ちょうどいい”お返しカタログを特集しています。
▶ 年末のご挨拶に欠かせない、喪中はがきのマナーと文例をまとめました。